こんにちは。
カントリージェントルマン鴨志田です。
2004年、東京井の頭から
軽井沢追分へ移住しました。
で、ネット上で、
こんなニュースを見かけました。


岩村田高等学校は、軽井沢っ子も通っていて、
わが家では、娘がお世話になりました。
わたしの教え子も通学中です。
そこで、ニュース記事、読んじゃいました。
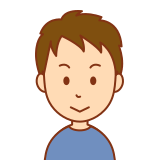
岩村田高等学校って
どんな学校なの?
そんな疑問・質問、よくわかります。
この記事を読むと、
●岩村田高校って、どんな学校なのか
●岩村田高校の受験データ
●岩村田高校のユニークポイント
がわかります。
そこで、まずは、結論から。
ニュースによると・・・

「こてさんね」「えぼをつる」…方言で苦労する介護職員向けに高校生がリーフレットとかるたを作成 佐久の岩村田高校
岩村田高校(佐久市)の2年生3人が佐久地方の方言をまとめたリーフレットと、方言のかるたを作った。介護施設で働く若い世代や地域外出身の職員が、高齢者の話す方言を分からないことがあると聞き、コミュニケーションに生かしてもらいたいと取り組んだ。活動の中で地域の介護施設を訪れ、方言がテーマだと皆で楽しく話せることを実感。作った物を喜んでもらえた手応えと同時に、方言を地域の文化として残したいという気持ちも芽生えた。
■介護現場で使いそうな言葉をまとめる。聞いたことのない方言ばかりで苦労
岩村田高校2年の松井陽奈(ひな)さん、渡辺優衣さん、梶蓮花(れんげ)さん=いずれも17歳=が作ったリーフレットは約50語を収録。片面で、A4かA3サイズに印刷する。介護職員にアンケートなどで尋ねた分かりにくい方言や、入浴や食事など、現場で使いそうな言葉を載せた。「こてさんね(たまらなくうれしい)肩をもんでもらって、こてさんね」「ももっかい(くすぐったい)背中がなんだかももっかい」など、方言、意味、例文を掲載。検索しやすいよう、五十音順と、動詞、名詞などの品詞順に並べたものを作った。
総合的な探究の時間を担当する草間千枝教諭が介護職員に方言を巡る苦労を聞き、生徒に投げかけたのがきっかけ。介護の仕事に関心がある、人の役に立ちたいなどの理由で3人が手を挙げた。
夏休みに、のぞみグループ(小諸市)が運営する小諸市の小規模多機能型居宅介護事業所「のぞみ」を訪問。職員に「方言が分からなくても、忙しくて手が回らない。助かる」と言われ、「実際にニーズがあると知り、真剣さが増した」(松井さん)。
収録する言葉を選ぼうと、昨年10月、職員や高齢者に聞き取り調査。よく話す言葉を聞くと、職員が「『おんぼさま(膝小僧)』って使いませんか?」と利用者に確認したり、高齢者が「店をやっていた両親が『いきやしょ(行きましょう)』と言っていた」と話してくれたりした。
方言の意味は草間教諭の父、文男さん(故人)が責任編集を務めた本「佐久地方で使われている方言」で調べた。梶さんは「聞いたこともない方言がほとんど。例文作りに苦労した」と話す。
■遊びを通じて弾む会話。地域文化への気付きも
昨年12月に完成して職員に渡すと「会話のきっかけになる」と喜ばれた。楽しんでもらおうと作った方言クイズも渡すと、頭や身体を動かせるかるたの制作を打診された。
かるた制作は元々視野にあり、「を」「ん」を除いた44枚の読み札を作り始めた。使う方言を決めて分担し、五七五の文章を検討。渡辺さんの「むずっけえ(くすぐったい) 裸足で歩く 泥の中」は昔の農作業を話すきっかけになると考えた。取り札は無料のイラストを使って作った。
1月28日、「のぞみ」で完成したかるたを高齢者と職員に見せた。生徒が「えぼをつる(すねる) ほんとはかまって ほしいだけ」と読むと、「少し発音が違うかな」「『えぼっつり』って言っていたよ」と会話が弾んだ。
交流後、松井さんは「高齢者とも職員とも心がつながった気がした。介護分野で働きたいので、将来使えそう」。梶さんは「方言は生活に根付いた言葉が多く、文化そのもの。大切な地域の言葉を残す意味もある」と強調した。
リーフレットは希望する佐久地方の介護施設に無償で配る予定。かるたの追加作成は未定だが、若い世代にも使ってもらう方法を検討する。
■方言で呼び起こされる昔の記憶。お年寄りは生き生き話す
岩村田高生がリーフレットとかるたを贈った小諸市の介護施設「のぞみ」では以前から、高齢者との会話のきっかけに方言を重視してきた。多くの人が方言を使っていた若い頃の記憶が呼び起こされ、自発的に話すことにつながるという。
利用者の中には普段、自宅で一人で過ごし、あまり会話をしない人もいる。介護福祉士の猪尾典加さん(40)は「無口な人も方言を切り口に話し始めることがある。頭を使うトレーニングになるほか、楽しく話して施設で気持ちよく過ごしてもらうことにもつながる」と話す。
のぞみの職員は現在12人で、県外出身者は3人。年齢も30~40代が半数以上で、県内出身でも日常で方言を使わない人が多い。方言を話題にしようとしても、知っている方言に限りがあった。
施設では生徒が作ったリーフレットを高齢者と一緒に見て、「しょうしい(恥ずかしい)って使ってました?」などと声をかけて活用。埼玉県出身で介護福祉士の須賀望さん(40)は「高齢者から昔の思い出がたくさん出てきて、生き生きと話してもらえる。私たちにとってもリーフレットやかるたは教科書になり、コミュニケーションの幅が広がった」と感謝していた。
佐久市の岩村田高校1・2年生、1年間の探求を発表
岩村田高校(佐久市)は、探究成果発表会を市佐久平交流センターで開いた。1、2年生ら約400人が参加。各グループが1年間取り組んできた探究テーマについて説明し、仲間同士で活発に意見交換していた。
ポスター発表のテーマは「人口減少を逆手にとった観光はできないか?」「地域の活性化と移住者にはどんな関係があるのか」など。「ケーキのまち」ともいわれる佐久の現状について取り上げたグループも多かった。「佐久のケーキの魅力を発信しよう」と地域の店舗のこだわりやお薦め品を調べたグループの1年渡辺杏さん(16)は発表後「地元の果物や食材を使っているお店が多いことが分かった」と話していた。
ホールの発表では、日頃の学習にも生かそうと、赤や青といった色で記憶力は変わるのか―について仮説を立てて検証した研究などがあった。
<信濃毎日新聞から引用>
すばらしい取組みですね。
岩高OGのわが家の娘は大学進学の際、
福祉系の学部に進み、ただ今、学び中。
後輩たちもがんばってるんだな~と
うれしく思いました。
岩村田高等学校って

基礎データ
- 校名
⇒長野県岩村田高等学校 - 住所
⇒佐久市岩村田1248号 - 最寄り駅
⇒岩村田駅(JR小海線) - 設立年月日
⇒1919年4月 - 共学・別学
⇒男女共学 - 設置学科
⇒普通科
岩村田高校の歴史
- 1919年(大正8年)
⇒岩村田町立岩村田実科女学校開校 - 1924年(大正13年)
⇒岩村田町立岩村田中学校が開校 - 1929年(昭和4年)
⇒岩村田町立岩村田実科女学校が岩村田町立岩村田高等女学校と改称 - 1948年(昭和23年)
⇒学制改革により、岩村田町立岩村田高等女学校が長野県岩村田城戸ヶ丘高等学校に、岩村田町立岩村田中学校が長野県岩村田高等学校となる - 1949年(昭和24年)
⇒長野県岩村田高等学校と長野県岩村田城戸ヶ丘高等学校が統合し、長野県岩村田高等学校となる - 1961年(昭和36年)
⇒機械科を設置 - 1963年(昭和38年)
⇒電気科を設置 - 1987年(昭和62年)
⇒電子機械科を設置 - 2015年(平成27年)
⇒普通科単独校となる
⇒工業科と臼田高校と北佐久農業高校が統合し長野県佐久平総合技術高等学校となる
受験データ<令和7年度入試>
後期選抜
- 募集
⇒定員200名 - 志願受付期間
⇒2025年2/26~28 - 志願変更受付期間
⇒3/3~5 - 学力検査等の実施期日
⇒3/11 - 面接等の実施期日
⇒3/11~12 - 入学予定者の発表期日
⇒3/21
倍率の推移
少子化の影響で、1倍をきる公立高校が多いのは、
長野県に限ったことではありませんよね。
軽井沢のある東信エリアだけでも、現在、
野沢北と野沢南、小諸と小諸商業の合併が
進んでいて、更なる再編もあり得る状況です。
もっとも、岩村田高校は、東信エリアで
上位の進学校で、しかも、
最寄駅からも近い立地。
過去5年間を見ると、高校のレベルの割には
倍率が1倍をきる年もありましたけど、
ここ数年、人気上昇傾向で、
倍率は上がってます。
後期選抜
- 2019年度
<200人募集/0.99倍>
295(10月)⇒262(1月)⇒194(2月)
⇒197人(3月) - 2020年度
<200人募集/1.00倍>
288(10月)⇒240(1月)⇒195(2月)
⇒200人(3月) - 2021年度
<200人募集/0.99倍>
322(10月)⇒262(1月)⇒198(2月)
⇒198人(3月) - 2022年度
<200人募集/1.03倍>
299(10月)⇒267(1月)⇒204(2月)
⇒205人(3月) - 2023年度
<200人募集/1.15倍>
295(10月)⇒284(1月)⇒246(2月)
⇒230人(3月) - 2024年度
<200人募集/1.06倍>
298(10月)⇒287(1月)⇒222(2月)
⇒212人(3月) - 2025年度
<200人募集/ ? 倍>
276(10月)⇒254(1月)⇒ ? (2月)
⇒ ? 人(3月)
岩村田高校のユニークポイント

▼岩村田宿
岩村田高校のある岩村田は、江戸時代、中山道で
江戸から22番目の宿場町。ちなみに、
我が家のある軽井沢追分も20番目の追分宿。
元々、ご縁があったのかもしれません。
▼岩高(がんこう)
地域の高校には、よく略称がありますよね。
例えば、軽井沢高校ならば軽高(かるこう)。
岩村田高校は岩高(がんこう)と呼ばれています。
中学生の頃、娘は、「がんこう」という響きが
あまり好きになれず、当初、志望校から
外してましたけど、今では、すっかり
岩高生(がんこうせい)になりました。
ちなみに、文化祭は岩高祭(がんこうさい)。
それと、岩村田高校は、(いわむらた)ではなく、
(いわむらだ)なのだそうです。
▼普通科単独校になってまだ10年
岩村田高校には、以前、普通科、
電気科、機械科、電子機械科がありました。
2015年、工業科は他校と統合して
佐久平総合技術高等学校になり、
岩高は、普通科単独校になりました。
▼創立100周年
2024年度で創立100周年を迎えました。
おめでとうございます!
まとめ:岩村田高等学校 介護現場で役に立つ方言のリーフレット&かるた作成

岩村田高校は佐久エリアで上位の公立校
岩村田高校は、佐久エリアで上位の公立進学校。
佐久エリアの普通科上位進学校といえば、
野沢北高校があります。もっとも、少子化、
最寄駅からの立地、野沢北と南の合併が
進行中であることなどから、今後、さらに、
人気や偏差値にも動きがあるかもしれませんね。
佐久エリアで、野沢北高校と岩村田高校の
今後の展開はどうなるのでしょうか?
社会の変化や、少子化の影響で、
令和7年度入試の後期選抜の倍率がどうなるか
注目したいと思ってます。
【おすすめ】ニーズに合わ子化は受験生にとってチャンス
長野県では、社会の変化や、少子化対応のため、
高校再編を進めています。わが家の息子や娘が
高校受験した数年前と比べても、さらに
少子化は進んでいて、ますます、倍率が
1倍をきる高校も増えることが予想されます。
これは、受験生にとっては、チャンスとも
言えます。高校のレベルの割には、
倍率が1倍をきったり、限りなく1倍に
近くなったりすることも、少なからず
見かけるからです。
受験は情報戦。新中3のみなさんも、
過去のデータと比較しながら、
倍率を味方につけることも、お忘れなく。
【おすすめ】ニーズに合わせ、賢くプロの力も活用
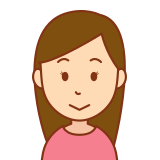
いつでもどこでも
最高の先生の授業が
受けられるなんて魅力的
プロの力を上手く使うのも
成績アップの早道ですよね!
軽井沢移住前の9年間、わたし、
栄光ゼミナール講師として、
数百人の教え子を送り出してきました。
軽井沢移住後、2009年4月、
こどもたちが小学生の頃、
追分こども会を立ち上げ、同時に、
地域で子育て教育アドバイザーとして、
活動も続けています。
そんな長~い受験指導の経験上、
こどもたちのニーズに合わせ、賢く、
などのプロの力を活用することも
おすすめします。







コメント